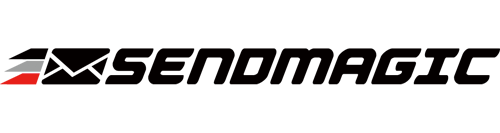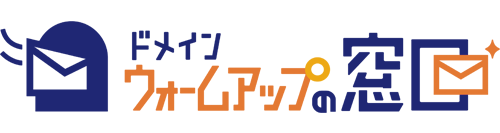“via.tokyo.jp”のような使い捨てメアドが、ドメイン評価を崩壊していく問題とは
昨今のオンラインサービスでは、「使い捨てメールアドレス」への対策が重要な課題となっています。使い捨てメールとは一時的に利用され、一定時間後に破棄できるメールアドレスのことです。
お客さまのプライバシー保護など有益ですが、企業側にとってはセキュリティやマーケティングの観点で無視できない問題を引き起こします。
日本では対策が遅れている使い捨てメールアドレスについて、世界の対応事例を踏まえ、なぜ使い捨てメールアドレス対策が必要なのか、そして効果的な対策方法について確認していきたいと思います。

使い捨てメールアドレスが抱える問題と対策が必要な理由
使い捨てメールアドレスが企業にもたらすリスクやデメリットには、主に以下のようなものが考えられます。
メール配信の効果低下に伴う送信ドメインへの悪影響
使い捨てアドレスは短期間で無効になるため、送ったメールが開封もされず高確率でエラー(ハード・ソフトバウンス)になります。
配信リストにこのようなアドレスが多いと送信ドメインの評価が下がり、他のお客さまへのメールまで迷惑メール判定される恐れがあります。
一時的に送信可能リスト増加は嬉しい感情を湧かせますが、長期的にはエンゲージメント率(開封率・クリック率)は極めて低くなり、期限切れアドレスへの送信で高いバウンス率に繋がり、悪影響の方が大きくなります。
マーケティングROIの悪化
使い捨てメールアドレスを登録するお客さまは、一度きりの目的(クーポン取得やコンテンツ閲覧など)を果たしたらそのアドレスを放置・破棄する傾向があります。
せっかくメルマガを配信しても登録解除されたり、あるいは完全放棄され、実質的な有益なお客さま育成に結び付かない死にアドレスが増えるだけです。
大量の無効・休眠アドレスを抱えると開封率やクリック率といった分析データも歪み、真のマーケティング効果が見えにくくなります。
こうしたジャンクなメアドを含んだ数字に惑わされると適切な施策判断を誤るリスクがあります。
お客さまとの信頼関係・エンゲージメントの問題
多くのお客さまが使い捨てアドレスで登録している場合、「自社ブランドを信用して本メールアドレスを預ける気になれない」ことの表れと考えるべきです。
実際、メールクリーニングサービスを提供している事業者による調査では
「多数の消費者が使い捨てを使うのは、そのブランドがデータを適切に管理しないのではという不信感や、後で大量のプロモーションメールを送りつけてくる懸念があるため」
と指摘されています。お客さまとの関係構築どころか、あなたのブランドに不信を招いている可能性があるわけです。
企業側のセキュリティ上のリスク
使い捨てメールは匿名性が高く、悪意のあるユーザーが多重アカウント作成や不正利用に使うケースもあります。
例えば無料の一括見積もりサイトでは、一人のユーザーが複数の使い捨てアドレスでアカウントを量産し、紹介キャンペーンの商品を不正取得したり、一人一回限定のクーポンや抽選応募に何度も参加するといった問題が起こりえます。
使い捨てアドレスの多くは誰でも受信箱を閲覧できる公開型サービスであるため、本来プライベートなはずのメール内容が第三者に見られる危険もあります。
実は、企業がお客さま向けに送ったキャンペーンメールや認証コードが、公開サイト上に晒されてしまうケースもあり得り、企業としてもマネージメントする必要があるメールアドレスなのです。
使い捨てメールアドレスを野放しにするとセキュリティ面・マーケティング面の双方で「短期的な得より長期的な損」が大きいことがわかります。
メール配信に関係するIT担当者とマーケティング担当者にとっては配信リストの健全性を損ない、結果として売上高やブランドイメージに影響します。そのため、世界中の企業がこの問題に対処すべく様々な対策を講じているのです。
世界ではどのように使い捨てメールアドレスを技術と運用で対処しているか
グローバル企業では、使い捨てメールアドレスへの対策として技術的なフィルタリングと運用ポリシーの両面からアプローチするのが一般的です。次に主要な有益な取組を紹介します。
リアルタイムでのメールドメイン検知・ブロック
もっとも基本的な対策は、新規ユーザー登録やメール購読用の入力フォームで使い捨てメールを弾くことです。これは、登録時にメールアドレスのドメイン部分をチェックし、既知の使い捨てメールサービスのドメインなら登録拒否をします。
例えば、当社がメールクリーニングサービスを通じて最も出会ってきた使い捨てメールアドレスは via.tokyo.jp です。
拒否するためのデータベースは社内でブラックリストを管理することもできますが、現実的には当社が提供するメールクリーニングサービスのAPIのように、リアルタイムAPIを利用して判定するケースが一般的です。
なお、判定用ドメインリストは非常に膨大かつ更新が頻繁です。
例えば、世界で提供されているあるサービスでは17万7千以上の使い捨てドメインを常時リスト化しており、新しいドメインも数時間以内に追加していると報告されています。世界中で次々と新規の捨てアド用ドメインが生まれているため、残念ながら手動での管理は非現実的です。
メールアドレスのクリーニングサービスによるリストの精査
世界でも、保有しているお客さまリストについては、最低年に1回。定期的にメールクリーニングサービスを行うのが推奨されています。
メールが届かずエラー(ハード・ソフトバウンス)になるアドレスや、一度も開封実績がないアドレスを放置すると送信リソースの無駄だけでなく送信ドメインの評価低下を招くためです。
メールクリーニングサービスを使えば、存在しないアドレスや使い捨てドメイン、スパムトラップの疑いがあるものを洗い出し、リストから除外できます。
日本でもまもなく1,000万通のメールクリーニングが実施されますが、世界では既に定期的なリストクリーンアップはメールマーケティングの基本的な衛生習慣として定着しつつあります。
日本でも良く使われるダブルオプトインの活用
登録時対策の一環として、ダブルオプトイン(二重の登録確認)は有効で、日本企業だけでなく、海外の企業でも広く使われています。
良くみる、サービスなどの利用者に入力してもらったアドレス宛に確認メールを送り、お客さまがメール内リンクをクリックしないと本登録が完了しない方式です。
存在しないアドレスやお客さまがアクセスできないアドレスでの登録を防げます。なお、多くの使い捨てアドレスは公開の受信箱で本人以外も閲覧可能なので要注意です。
登録リストの品質向上に寄与し、ボットやスクリプトによる無差別な捨てアド登録のフィルタ効果も期待できます。
ただし、悪意ある利用者が受信箱を開いて確認リンクをクリックしてしまえば突破される点は留意が必要です。
ダブルオプトインは使い捨てメール対策の万能薬ではありませんが、全体として無効アドレス流入を減らす副次的メリットがあります。
ユーザーへの透明性と信頼醸成
技術的にブロックするだけでなく、お客さまがメインのメールアドレスを使いたくなる環境作りも重要です。
例えば、登録フォーム付近に「メールアドレスの安全な管理方針」などを示したり、プライバシーポリシーをわかりやすく提示することで、サービス利用者の不安を和らげることができます。
メール配信内容についても、事前にアナウンスしている週1回のメルマガのみを送信するという誠実な運用を守ることが大切です。
実際、良質なコンテンツをお客さまに価値を届けている限り、わざわざ使い捨てアドレスで受け取ろうとは思わないはずです。
「この企業からのメールなら本アドレスできちんと受け取って見たい!」
と感じてもらえれば、結果的に使い捨てアドレスの利用抑止につながります。
使い捨てアドレス利用時の社内ルール
使い捨てメールアドレスを完全にブロックせず、メール配信を続ける場合でも、扱いについて社内でルール化しておくと良いでしょう。
例えば「使い捨てと判明したアドレスには3通だけメール送信し、開封が無ければその後は配信リストから除外する」といった方針です。
日本国内の使い捨てのメールアドレスでも、バウンスをしないCatch-All設定になっているメールアドレスがあります。つまり、送ってエンゲージメントがあるかどうかで判断するしかないのです。
日本は約10年遅れ..。海外企業・サービスに見る使い捨てメールアドレス対策
世界の企業やプラットフォームは、使い捨てメールアドレスに対してさまざまな形でマネジメントを行っています。その背景には、
- セキュリティリスクの低減
- マーケティング効果の最大化
- ユーザーエンゲージメントの向上
といった複合的な目的があります。主要地域と業種でどのような取り組みをしているかご紹介します。
SNS・ゲームプラットフォームでの徹底排除
アメリカの主要SNSであるXやFacebookでは、使い捨てメールアドレスでのアカウント登録を原則として禁止しています。
実際にXでは、使い捨てメールアドレスによる登録試行時にエラーが出たり、アカウントがすぐに凍結されたりするとの報告が確認されています。
これは、不正な複数アカウントの作成を防止し、プラットフォーム全体の健全性を守るためです。
同様に、PlayStation Networkなどのゲーム系プラットフォームでも使い捨てメールアドレスの使用は禁止されており、検知された場合はアカウント停止に至ることもあるようです。
こうしたサービスでは、早期から使い捨てメールアドレス排除の仕組みが整備されており、不正アクセスや迷惑メールを配信するアカウントへの高い警戒心が伺えます。
小売・ECサイトによる不正利用を排除するビジネス設計
EC業界でも使い捨てメールアドレス対策は進んでおり、とくに初回購入割引やキャンペーン特典の乱用を防ぐために、特別な措置を講じています。
米国の一部小売企業では、割引目的での一時登録と即離脱を防ぐため、「初回特典を2回目以降の購入で適用」に変更したケースもあります。
また、懸賞やキャンペーンでは、応募ごとにメール確認やIP制限を課すことで、多重応募を防止しています。これは単なるメールをブロックすることにとどまらず、インセンティブ設計そのものを見直すというビジネス側の対策です。
一方で、ヨーロッパではGDPRの影響もあり、お客さまから配信同意を得たメールアドレスにしか配信しない運用が一般化しています。結果として「使い捨てアドレスを使わなくても安心」という心理的ハードルの低下にもつながっています。
メールサービス業界はエイリアス機能とプライバシーの両立
近年では、メールプロバイダ自体も使い捨てメールアドレスに近い「メール エイリアス機能」を提供しています。
例えば、Gmailの「メール エイリアス」。さらに、AppleのiPhoneでも使える「Hide My Email」やFirefox Relayなども、ユーザーのプライバシー保護を目的に中継メールアドレスを発行しています。
一見すると通常のアドレスに見えるこれらの中継機能は、企業側からすれば
「いつでも破棄できるメールアドレス」
となり、お客さまとの長期的な関係構築が難しくなる要因にもなりかねません。
そのため、欧米の企業ではこうしたエイリアス機能を使い、使い捨てメールアドレスで登録してくるお客さまを「慎重派」と捉えたうえで、信頼醸成型のマーケティングを行う戦略が求められています。
日本における対応の遅れ
日本では「メルアドぽいぽい」や「InstAddr(インスタントアドレス)」などの使い捨てメールサービスが人気で、誰でも複数のアドレスを即時発行・破棄できます。
これらのサービスは独自ドメイン(例:@usako.net、@svk.jpなど)を多数抱えており、次々と新ドメインを投入されるため、ドメインベースでのブロックも限界があります。
サービス運営者からも、
「海外のプラットフォームでは登録が拒否されるため、新ドメインや期間限定機能で対応しています」
と明言しており、海外対策と使い捨てメールアドレスの提供側とのいたちごっこが続いているのが現状です。
日本国内では、使い捨てメールアドレスに対する企業側の対策が遅れており、使い捨てアドレスでの登録が容易なサイトも多く見られます。
その結果、「送信ドメインの評価が下がる ➡️ マーケティングメールが届かない ➡️ 開封率が下がる ➡️ さらにはECでの不正注文が増える」
といった副作用が顕在化しています。届くメールを維持するためにも、このような使い捨てメールアドレスは排除していく必要があるのです。
最後に
使い捨てメールアドレスへの対策は、一見地味なようですが送信メールのドメイン評価(マーケティングの投資対効果)と企業のセキュリティを守る上で非常に重要です。
世界では既に多くの企業がリアルタイムブロックやメールクリーニングサービスを導入し、「本物のお客さま」と健全な関係を築く努力を何年も前から取り組んでいます。
日本においても世界における取組を参考にしつつ、適切なツール活用と運用ポリシー整備を進めることで、無駄のない効率的なメールコミュニケーションを実現できるはずです。
重要なことは、単に使い捨てメールアドレスを受付ないだけでなく「なぜお客さまが捨てアドを使うのか」を理解し、自社の改善に活かすことです。
あなたのブランドが確立されれば、お客さまはメインのメールアドレスで喜んでコミュニケーションを取ってくれるはずです。使い捨てメールアドレス対策をきっかけに、自社のメール運用を今一度見直してみてはいかがでしょうか。